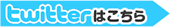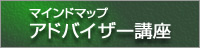経営後継者や事業者、ビジネスリーダー、専門家向けに「経営」を「企画」で解決する専門家。
シニアマインドマップインストラクター(シニアTLI)、
デザイン出身の中小企業診断士、松岡 克政(まつかつ)のWebサイトです。
シニアマインドマップインストラクター(シニアTLI)、
デザイン出身の中小企業診断士、松岡 克政(まつかつ)のWebサイトです。
⇒ トップリーダー養成塾説明会
⇒ 2017年イベント情報
▼ 2008/07/20(日) 入院中の読書と、いつものごとく、フォトリーディング、マインドマップなど
まつかつ@病院です。
さっきの投稿「2週間強の期間、入院しての現状報告」の続きです。
■今考えることといただいた本
そして、今まで考えることから逃げてきた「死」とかについても、
今は考えるいい機会だとも思っている。
お見舞いに来てくれた方たちからいただいた素敵な本にも、
実はそういう部分に関係するところがある。本当に偶然なんだけど。
 目に見えないけれど大切なもの―あなたの心に安らぎと強さを (PHP文庫)
渡辺 和子
目に見えないけれど大切なもの―あなたの心に安らぎと強さを (PHP文庫)
渡辺 和子
Jさん、ありがとうございました。
じんわり深く、今の僕にぐっと来ました。
そして、偶然この本にも記述があった下記本。
 夜と霧―ドイツ強制収容所の体験記録
V.E.フランクル,霜山 徳爾
夜と霧―ドイツ強制収容所の体験記録
V.E.フランクル,霜山 徳爾
僕のデザイン事業パートナー、木全さんからの贈り物、彼の座右の書です。
僕も『7つの習慣』を読んだころから、いつか絶対読みたいと思っていた本です。
さすがに手術前は読むのはきついと思っていたんだけど、もう第三ステップ:フォトリードは済ませてあるので、あとはじっくり読むタイミングを待つのみ、です。
こういった本を通して、あるいは病室のおじいさんたち、あるいは患者さんの話を通して、この機会にじっくりと考えてみたいと思っています。
■その他の読書と、例のごとく、フォトリーディング、マインドマップ、ジーニアスコードについて
その他今(たった今、この2,3日という感じね)読んでいる本は、情報デザインに関する本。

 それは「情報」ではない。―無情報爆発時代を生き抜くためのコミュニケーション・デザイン
リチャード・S. ワーマン
それは「情報」ではない。―無情報爆発時代を生き抜くためのコミュニケーション・デザイン
リチャード・S. ワーマン
この本は6年前に買っているんだけど、初めてしっかり読んでいる。
著者、リチャード・S. ワーマンは僕が将来そうなりたいと思える人の一人。
とっても素敵な生き方とアウトプットの方。
合わせて一緒にしシントピックリーディングしようと思っていたのが、この巨匠の本。
 知の編集工学 (朝日文庫)
松岡 正剛
知の編集工学 (朝日文庫)
松岡 正剛
松岡正剛氏は、僕の叔父さんにあたる人、 というのはウソ(笑)。
もしかしたら家系図をたどって行くと、遠い親戚だと判明するかもしれない。
期待を込めて。
実は、僕の前職場、「日立製作所 デザイン研究所(現 デザイン本部)」では、松岡正剛氏とんほ共同研究をしていて、僕はその取り組みを、ひっじょおおおおおに興味深く遠巻きに見ていました。
(当時入社したばかりだったからね)。
そのときからの憧れの人です。
で、僕が買った1996年にはハードカバーだったんだけど、今は文庫なんだね。
どちらの本も、僕がフォトリーディングを知らなかったら、とっても読みきらずに積読(つんどく)だけになっていた本。
これらの本のフォトリーディングとマインドマップ化については、記録をとっていくので、後でフィードバックできるといいな。
実は僕はフォトリーディングとマインドマップはセットにしないほうがいいと思っているタイプの人間なんだけど、今回「それは「情報」ではない。―無情報爆発時代を生き抜くためのコミュニケーション・デザイン」をマインドマップと平行して読むことで新しい境地を見出した(ちょっとおおげさかな?)。
あるいは、入院中の投稿「初めて書いたマインドマップによる読書感想文(不謹慎でゴメン)()」で、

クリックすると画像が大きく表示されます。
読書後に書くマインドマップがどれだけ自分の内面の感想を引き出しているかを目の当たりにしてしまったことを考えると、
はたまた「フォトリーディングの神髄について力説!with点滴(笑)」や、
「小説『夜のピクニック』読了と、今の僕の小説の読み方」、
少しだけ論点がずれるけど、
「ヒッポとフォトリーディングとマインドマップの共通項1」なども考えると、
フォトリーディングとマインドマップの関係性について、さらに深い、今までと違った考察が出来ている時間のような気がする。
何回も書いているように、フォトリーディング(≒インプット)、マインドマップ(≒アウトプット)、さらにはジーニアスコード(≒スループット、頭の内部強化)のツールを用いて、「脳力」を強化していくことで、とても面白い、可能性に満ち満ちた人生のプロジェクトにたくさん関われるようになる確信がある。
そういった考察においても、こういう、効率的なアウトプットにとらわれない時間が意味を持つのでしょう。
当初、書こうとしていたことかなあ?
まあ、いいや。もうじき夕飯の時間です。
今日の午後の時間は、とても有意義、退屈せずに脳をフル稼働して過ごせました、とさ。
さっきの投稿「2週間強の期間、入院しての現状報告」の続きです。
■今考えることといただいた本
そして、今まで考えることから逃げてきた「死」とかについても、
今は考えるいい機会だとも思っている。
お見舞いに来てくれた方たちからいただいた素敵な本にも、
実はそういう部分に関係するところがある。本当に偶然なんだけど。
 目に見えないけれど大切なもの―あなたの心に安らぎと強さを (PHP文庫)
渡辺 和子
目に見えないけれど大切なもの―あなたの心に安らぎと強さを (PHP文庫)
渡辺 和子Jさん、ありがとうございました。
じんわり深く、今の僕にぐっと来ました。
そして、偶然この本にも記述があった下記本。
 夜と霧―ドイツ強制収容所の体験記録
V.E.フランクル,霜山 徳爾
夜と霧―ドイツ強制収容所の体験記録
V.E.フランクル,霜山 徳爾僕のデザイン事業パートナー、木全さんからの贈り物、彼の座右の書です。
僕も『7つの習慣』を読んだころから、いつか絶対読みたいと思っていた本です。
さすがに手術前は読むのはきついと思っていたんだけど、もう第三ステップ:フォトリードは済ませてあるので、あとはじっくり読むタイミングを待つのみ、です。
こういった本を通して、あるいは病室のおじいさんたち、あるいは患者さんの話を通して、この機会にじっくりと考えてみたいと思っています。
■その他の読書と、例のごとく、フォトリーディング、マインドマップ、ジーニアスコードについて
その他今(たった今、この2,3日という感じね)読んでいる本は、情報デザインに関する本。

 それは「情報」ではない。―無情報爆発時代を生き抜くためのコミュニケーション・デザイン
リチャード・S. ワーマン
それは「情報」ではない。―無情報爆発時代を生き抜くためのコミュニケーション・デザイン
リチャード・S. ワーマンこの本は6年前に買っているんだけど、初めてしっかり読んでいる。
著者、リチャード・S. ワーマンは僕が将来そうなりたいと思える人の一人。
とっても素敵な生き方とアウトプットの方。
合わせて一緒にしシントピックリーディングしようと思っていたのが、この巨匠の本。
 知の編集工学 (朝日文庫)
松岡 正剛
知の編集工学 (朝日文庫)
松岡 正剛松岡正剛氏は、僕の叔父さんにあたる人、 というのはウソ(笑)。
もしかしたら家系図をたどって行くと、遠い親戚だと判明するかもしれない。
期待を込めて。
実は、僕の前職場、「日立製作所 デザイン研究所(現 デザイン本部)」では、松岡正剛氏とんほ共同研究をしていて、僕はその取り組みを、ひっじょおおおおおに興味深く遠巻きに見ていました。
(当時入社したばかりだったからね)。
そのときからの憧れの人です。
で、僕が買った1996年にはハードカバーだったんだけど、今は文庫なんだね。
どちらの本も、僕がフォトリーディングを知らなかったら、とっても読みきらずに積読(つんどく)だけになっていた本。
これらの本のフォトリーディングとマインドマップ化については、記録をとっていくので、後でフィードバックできるといいな。
実は僕はフォトリーディングとマインドマップはセットにしないほうがいいと思っているタイプの人間なんだけど、今回「それは「情報」ではない。―無情報爆発時代を生き抜くためのコミュニケーション・デザイン」をマインドマップと平行して読むことで新しい境地を見出した(ちょっとおおげさかな?)。
あるいは、入院中の投稿「初めて書いたマインドマップによる読書感想文(不謹慎でゴメン)()」で、

クリックすると画像が大きく表示されます。
読書後に書くマインドマップがどれだけ自分の内面の感想を引き出しているかを目の当たりにしてしまったことを考えると、
はたまた「フォトリーディングの神髄について力説!with点滴(笑)」や、
「小説『夜のピクニック』読了と、今の僕の小説の読み方」、
少しだけ論点がずれるけど、
「ヒッポとフォトリーディングとマインドマップの共通項1」なども考えると、
フォトリーディングとマインドマップの関係性について、さらに深い、今までと違った考察が出来ている時間のような気がする。
何回も書いているように、フォトリーディング(≒インプット)、マインドマップ(≒アウトプット)、さらにはジーニアスコード(≒スループット、頭の内部強化)のツールを用いて、「脳力」を強化していくことで、とても面白い、可能性に満ち満ちた人生のプロジェクトにたくさん関われるようになる確信がある。
そういった考察においても、こういう、効率的なアウトプットにとらわれない時間が意味を持つのでしょう。
当初、書こうとしていたことかなあ?
まあ、いいや。もうじき夕飯の時間です。
今日の午後の時間は、とても有意義、退屈せずに脳をフル稼働して過ごせました、とさ。
【MK10】メルマガバックナンバー
まつかつの独立10周年を記念したメルマガバックナンバー ⇒こちら
メルマガのお申し込みはこちら
マインドマップ他お役立ち情報をお届けします!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⇒ 2017年イベント情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆トップリーダー養成塾 第4期 成果発表会◆
この養成塾で得た学び・気付きの集大成の塾生プレゼンテーション。
参加者さまと一緒に『場』を楽しむ構成になっています。
是非、この『場』と塾生の成果をリアルに感じてみてください。
2017年6月18日(日)
⇒お申し込みはこちらへ