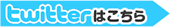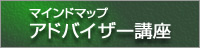経営後継者や事業者、ビジネスリーダー、専門家向けに「経営」を「企画」で解決する専門家。
シニアマインドマップインストラクター(シニアTLI)、
デザイン出身の中小企業診断士、松岡 克政(まつかつ)のWebサイトです。
シニアマインドマップインストラクター(シニアTLI)、
デザイン出身の中小企業診断士、松岡 克政(まつかつ)のWebサイトです。
⇒ トップリーダー養成塾説明会
⇒ 2017年イベント情報
▼ 2005/10/15(土) ひさびさにまじめに-今後のBLOG内容の構想
まつかつです。
最近ちょっと自分自身乱れていたというか、ふぬけていたというか、なんとも情けない状態となっていました。
自分のそのときの状況を書くだけならそれでもいいのでしょうが、502教室経由で勉強時間を割いて来てくださる方たちのことを考えると、それはちょっと雑すぎるゾ、と。
そこで、今後書いていく方向性を再整理しようと思います。
●一次試験用ノウハウの再整理
前回概要を軽く書きました。Okさん曰く、私の勉強方法の独自性は(あるとすれば)、「機会を増やす」だそうです。
そのことを含め、本項目の内容は、自分自身でもその方法論を強く意識してやっていたので書きたい気持ちいっぱいなのですが、逆に、なんかやりたいことややるべきことがたくさんあるような気がして、かえって気後れしてしまっている現状です。BLOGらしく気軽に書いていくのが良いのでしょう。大上段に構えずサラッとね。
●勉強開始から二次試験受験までの流れ
みなさんそれぞれに固有のドラマがあったと思います。そしてもちろん私にも紆余曲折というかターニングポイントがあったはず。
そしてそれは2004年11月からほぼ毎日続けてきたBLOGからひもとくことが出来るはずです。(自分としては、そうなるようにと、毎日そのときに感じたことを率直に書いてきました。)
そういったポイントを振り返ってみながら、何かみなさんの参考になることがあるかもしれないと思ったりしています。
●二次試験後のゆれる心境
冒頭に「乱れている」と書きましたが、それはそれで、絶対に今しか体験できない領域なので書く必要はあると勝手に思っています。もう少しみなさんに有用な情報になるようには意識しながら。
●二次試験結果発表までの取り組み実態
二次試験筆記は終わった。じゃあそのつきに何をどう取り組んでいくの?
何か事を成し遂げるときに大事なのは、「アクセルを吹かすこと」よりも「ブレーキをいかに踏むか」だと思います。もっと言うと「どこのブレーキを踏み、どの部分はアクセルを吹かした勢いを保ち続けるか」(例えが悪いので言い換えると、ブレーキを踏みながらも、アクセルを踏んだことで強化された数々の部分《例:足回りやタイヤ、高性能ライト、危険防止察知能力、軽量化、はたまた室内装備等》のどこはキープし続け、どれはダウングレードしても良いと判断すること)を的確に選択することだと思います。
書いてみて思ったけど、目の前の目標を失って戸惑っている今、次に意識すべきはそのことかもしれません。
基本的には、中小企業診断士合格よりも、もっともっと大きな目標をみながらやってきているのですが、それでも現実はこんなもん(モチベーション低下)です。だからこそ、その戸惑いの中からどうやって先へと進んでいくかを真剣に考え、BLOGに書いていくことが有意義かもしれません。
●その他
たとえばBLOGを書いたことの効用、会社と家庭との両立や相乗効果、モチベーション維持、健康法、他、色々あります。
中小企業診断士合格目標に結び付けて、自分を高めるために意識した事柄などです。
ここまで書いてみて思ったこと。
書くことで次にやるべきことはかなりクリアーになったけど、一方で大上段に構えそうな自分がいます。
別に大それた事をしてきたわけでもなし、淡々とそのとき思うことを楽しみながら書き続けるのがいいのでしょう。
振り返るのって、楽しいけれど、まとめるのはかなりパワーがいります。あれもこれもと言いたい事が出てくるけれど、閲覧者が読みたいのは自分に役立つことだけなはず。
それを意識しながらも、やっぱり思うことを書き続けるのだろうな。
→あれ、結局何も変わってないや(笑)。
ああ、そうです。何か要望等あればコメントにお書きください。前向きに検討いたします。むろん出来ることしか出来ませんし、気分屋なので、、、その辺をご了承願えればということですが。
せっかくのインターネットの「双方向性」ですからね。
ふう、今日は考えながら書いたので30分も!かかってしまったぞ。いくら時間が少し出来たからとはいえ、こんな書き方じゃ長続きしないから、やっぱりたいそうなことはかけないや。
なんにせよ、
今後も懲りずによろしくお願いいたします。
最近ちょっと自分自身乱れていたというか、ふぬけていたというか、なんとも情けない状態となっていました。
自分のそのときの状況を書くだけならそれでもいいのでしょうが、502教室経由で勉強時間を割いて来てくださる方たちのことを考えると、それはちょっと雑すぎるゾ、と。
そこで、今後書いていく方向性を再整理しようと思います。
●一次試験用ノウハウの再整理
前回概要を軽く書きました。Okさん曰く、私の勉強方法の独自性は(あるとすれば)、「機会を増やす」だそうです。
そのことを含め、本項目の内容は、自分自身でもその方法論を強く意識してやっていたので書きたい気持ちいっぱいなのですが、逆に、なんかやりたいことややるべきことがたくさんあるような気がして、かえって気後れしてしまっている現状です。BLOGらしく気軽に書いていくのが良いのでしょう。大上段に構えずサラッとね。
●勉強開始から二次試験受験までの流れ
みなさんそれぞれに固有のドラマがあったと思います。そしてもちろん私にも紆余曲折というかターニングポイントがあったはず。
そしてそれは2004年11月からほぼ毎日続けてきたBLOGからひもとくことが出来るはずです。(自分としては、そうなるようにと、毎日そのときに感じたことを率直に書いてきました。)
そういったポイントを振り返ってみながら、何かみなさんの参考になることがあるかもしれないと思ったりしています。
●二次試験後のゆれる心境
冒頭に「乱れている」と書きましたが、それはそれで、絶対に今しか体験できない領域なので書く必要はあると勝手に思っています。もう少しみなさんに有用な情報になるようには意識しながら。
●二次試験結果発表までの取り組み実態
二次試験筆記は終わった。じゃあそのつきに何をどう取り組んでいくの?
何か事を成し遂げるときに大事なのは、「アクセルを吹かすこと」よりも「ブレーキをいかに踏むか」だと思います。もっと言うと「どこのブレーキを踏み、どの部分はアクセルを吹かした勢いを保ち続けるか」(例えが悪いので言い換えると、ブレーキを踏みながらも、アクセルを踏んだことで強化された数々の部分《例:足回りやタイヤ、高性能ライト、危険防止察知能力、軽量化、はたまた室内装備等》のどこはキープし続け、どれはダウングレードしても良いと判断すること)を的確に選択することだと思います。
書いてみて思ったけど、目の前の目標を失って戸惑っている今、次に意識すべきはそのことかもしれません。
基本的には、中小企業診断士合格よりも、もっともっと大きな目標をみながらやってきているのですが、それでも現実はこんなもん(モチベーション低下)です。だからこそ、その戸惑いの中からどうやって先へと進んでいくかを真剣に考え、BLOGに書いていくことが有意義かもしれません。
●その他
たとえばBLOGを書いたことの効用、会社と家庭との両立や相乗効果、モチベーション維持、健康法、他、色々あります。
中小企業診断士合格目標に結び付けて、自分を高めるために意識した事柄などです。
ここまで書いてみて思ったこと。
書くことで次にやるべきことはかなりクリアーになったけど、一方で大上段に構えそうな自分がいます。
別に大それた事をしてきたわけでもなし、淡々とそのとき思うことを楽しみながら書き続けるのがいいのでしょう。
振り返るのって、楽しいけれど、まとめるのはかなりパワーがいります。あれもこれもと言いたい事が出てくるけれど、閲覧者が読みたいのは自分に役立つことだけなはず。
それを意識しながらも、やっぱり思うことを書き続けるのだろうな。
→あれ、結局何も変わってないや(笑)。
ああ、そうです。何か要望等あればコメントにお書きください。前向きに検討いたします。むろん出来ることしか出来ませんし、気分屋なので、、、その辺をご了承願えればということですが。
せっかくのインターネットの「双方向性」ですからね。
ふう、今日は考えながら書いたので30分も!かかってしまったぞ。いくら時間が少し出来たからとはいえ、こんな書き方じゃ長続きしないから、やっぱりたいそうなことはかけないや。
なんにせよ、
今後も懲りずによろしくお願いいたします。
【MK10】メルマガバックナンバー
まつかつの独立10周年を記念したメルマガバックナンバー ⇒こちら
メルマガのお申し込みはこちら
マインドマップ他お役立ち情報をお届けします!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⇒ 2017年イベント情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆トップリーダー養成塾 第4期 成果発表会◆
この養成塾で得た学び・気付きの集大成の塾生プレゼンテーション。
参加者さまと一緒に『場』を楽しむ構成になっています。
是非、この『場』と塾生の成果をリアルに感じてみてください。
2017年6月18日(日)
⇒お申し込みはこちらへ