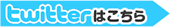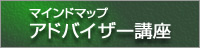シニアマインドマップインストラクター(シニアTLI)、
デザイン出身の中小企業診断士、松岡 克政(まつかつ)のWebサイトです。
⇒ トップリーダー養成塾説明会
⇒ 2017年イベント情報
▼ 2008/07/10(木) フォトリーディングの神髄について力説!with点滴(笑)
おはようございます。まつかつ@病院@ケータイです。
なんとかすっきり目覚めました。さあて、今日はいっぱい書くぞぉ、の気持ち(笑)。
痛み止めがきれて、痛くなる予感、だけど楽しいことをして痛みを忘れるのだ!
、、、という意味では準備はぬかりなくやってきた、と言えるかも。
今日用の小説3冊はフォトリーディングしてそして後書きを読んで、興味を募らせて、どれをいつ読もうか当たりをつける(笑)。
病院に持参している本は約40冊(笑)。看護婦さんが本がスーツケースいっぱいに入ってるのを見たとき、たいそうびっくりしていた。
血とか内蔵とか平気な人たちなのに(笑)。
***この間に手術準備のための浣腸と(汚くてすみません)点滴をやられる***
持参したほとんどの本はすでにフォトリード(第三ステップね)を済ませてある。
小説も当然フォトリードしてから高速リーディング。(ということで5つくらい前の投稿のマインドマップによる読書感想文ってやつも当然フォトリードずみ。 ウィズさん、Ok?)
とはいっても、本当にひさしぶりの 時間 なので別に 高速 にはこだわらない。
いつも ある意味 高速 なんだからこんな時くらい 時間気にせず読んでもいいでしょ?
とはいえ、今までに病院で読んだ(情報処理した)小説以外の本は5冊くらい、(それぞれ結構分厚いよ。)とても意義深いものでした。
こういう機会だから一つ一つ、どんな風にアプローチしてどう言う部分を取り込んだのか書きたいけど、左手に刺している点滴が邪魔(笑)。
フォトリーディングのいいところは、いくつもあるけど、今この文脈で記すと、、、
・著者と自分と対話をしながらの主体的な読書
・(それによるところも大だが) 自分の過去の得た情報が今ここで再再生される感じ 感覚的に言うと「ああ、つながった!」 という感じ。
よく指摘を受けるので、ここでも主張したいけどフォトリーディングは、軽薄短小な情報処理術では、ない。
その神髄はヒューマ二ティーあふれる人間と情報との関わり、学び方を学ぶプロトコル(手順)、自分(の持っている人としての能力)を信じること、それにより、、、 ここではこれ以上はやめよう((笑)。
どんな道具、方法論でもそうだけど 「使いよう」 だよね?メスとなるかドスとなるか。
それを理解するには、やはり開発者の真意とそのツールの神髄までも知るのがいい。
そんな時間ない??
じゃあフォトリーディングしてごらん(笑)。著者に「このツールの神髄はなんですか?」って。そしたら著者はあなたに教えてくれるから。15分程度、本を通して、直接対話をすることで。
あなたも著者も(?)忙しい。
だから、また会いたくなるまで本は本棚へ!
でも興味があったら、また会いたくなるでしょ!そしたらまた会えばいいんです。15分でも30分でも。
そうやって、たくさんの著者に会いながらあなたにとっての座右の書と出会っていくんです。そして、その座右の書は、ふと思い立ったときに、あなたにいろんな事を教えてくれます。
そんな本との関係を造るのにフォトリーディングは役立つんです。
だって100冊から5人選ぶのと1000冊から5人選ぶの、どっちも選択できるならどっちを選ぶ?
そのときあなたは著者の生い立ちから昔話、聞く必要はない。ダイレクトに、あなたが一番知りたいことだけを著者から直接聞くんです!
その結果の伴侶 5人(人数に他意はありません)。
どう?
こういうこともフォトリーディングを通してお伝えしたいことのひとつ。スキルから順番に、そしてその先へ。。。
***体勢の悪さ 点滴の手を持ち上げていること に疲れ、読書へ***
小説の世界に引き込まれています。浅田次郎 地下鉄に乗って
やべ、また泣いちゃうのかな(笑)。
ここまで、いろいろあったので約2時間かかっちゃいました(笑)
-----------------sent from W-ZERO3
【MK10】メルマガバックナンバー
まつかつの独立10周年を記念したメルマガバックナンバー ⇒こちら
メルマガのお申し込みはこちら
マインドマップ他お役立ち情報をお届けします!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⇒ 2017年イベント情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆トップリーダー養成塾 第4期 成果発表会◆
この養成塾で得た学び・気付きの集大成の塾生プレゼンテーション。
参加者さまと一緒に『場』を楽しむ構成になっています。
是非、この『場』と塾生の成果をリアルに感じてみてください。
2017年6月18日(日)
⇒お申し込みはこちらへ